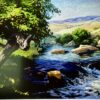自然は癒し効果抜群
暑い夏休み
子ども達は夏休みをどのように過ごされましたでしょうか? 田舎に帰る、旅行、プール三昧、のんびり、勉強一本等々色々なことができたかも知れませんが、ここのところの暑さは子ども達にも大きな悪影響を与えたかもしれません。
それに2020年からのコロナの時期は楽しい夏休みを経験できなかった子ども達もいることでしょう。
夏のお楽しみ会
教会では7月26日(土)にジュニア教会(教会学校)の「夏のお楽しみ会」をしました。今年はとても暑いので、教会堂内だけで行うことにしました。
子ども達5名の参加者があり、11時から焼きそば作りを一緒にしました。みんなにも包丁を持ってもらい野菜を切るところからスタートでした。なかなか美味しいのができてみんな満足でした。その後、射的や金魚?すくい、ゲームをして楽しく遊び、西瓜割りをしました。実に大笑い連続で楽しかったです。その西瓜をおやつにたっぷりいただいて、聖書のお話を聞きました。「ザアカイさん」のお話にみんな聞き入り色々な反応があり、子ども達も成長したなあと思いました。最後に工作をしました。みんなすごい集中して作るので、スタッフの私達が驚いてしまうほどでした。なんとか4時に終えて、無事に帰宅していただきました。
夏休みの思い出
こんなに暑い夏は私も人生70年でで初めてです。子どもの頃の夏休みが懐かしく、思い出されてなりません。
「夏の友」という宿題帳があって、毎日それをするのですが、気温を書き込むことがあって、とても暑かった日に「32度」と書き込んだことを覚えています。何しろクーラーのない時代です。朝夕は涼しかったです。
高校3年生の夏休みも小学校のグランドに行って、サッカークラブの子ども達と一緒にサッカーをしていました。私も子ども達も「熱中症」になることもなく、夕方になるまで汗だくになってサッカーをしていたことを思い出します。
夏休みの宿題で一番嫌だったのは「読書感想文」でした。高校を卒業するまで本を読むのが嫌いでした(大学に入って、クリスチャンになって一気に本好きになるのですが)。しかも、感想文をほめてもらったことがありませんでした。
俵万智さんの本
ところで、この夏に読んだ「生きる言葉」(俵万智著 p24-27)に俵さん御自身の子育てが書いてありました。
自然の中で「めいっぱい遊ぶ」
生身か受け身かという点では、ゲームも要注意な強敵だ。ゲームの中では、いくら動いても、風や匂いや痛み等を感じることはない。決められたルールの中で、決められたことをクリアしてゆく。そこにストーリー性があったり、仲間との連帯という喜びがあったりするのは理解できるが、そればっかりで子ども時代を過ごすのはもったいない。五感を刺激されることで、成長してゆく時期なのだから。
ゲームについては、息子もやりたがってキリがなかったので一計を案じた。
「ゲームが面白いのは、わかる。でもね、これはおやつなんだよ。ケーキやチョコレートと同じ。おいしいからって、朝はケーキ、昼はポテチ、夜はチョコレートだったら、大きくなれないし、病気になってしまうよ。だからゲームも、おやつみたいに分量と時間を決めて、楽しくやろう」
このたとえは説得力があったようで、息子も「うまいこと言うね!」と納得していた。そしてゲームをした時間と同じだけ本を読むというルールも付け加えた。頭ごなしに否定したり、規則を押しつけたりするのでなく、「おやつ」という身近な比喩は、子どもの心をとらえてくれたようである。
その後、小学二年生から、縁あって沖縄の石垣島に住むようになったのだが、いつのまにか息子はゲームをしなくなった。「そういえば最近、全然ゲームしないね」と言うと、おやつ以上にうまい答えが返ってきた。「だってお母さん、オレが今マリオなんだよ!」。「オレが今マリオなんだよ」島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬ
大自然の中で、友だちと一緒に暗くなるまで遊びほうける日々。滝つぼに飛びこみ、海で釣りをし、サトウキビ畑で鬼ごっこ。その冒険は、まさに自分自身がゲームの主人公になったような気分だったのだろう。五感をフルに活用することは、言葉を鍛える土台のようなものではないか、と思う。「めいっぱい遊ぶ」ことは、机の上の勉強と同じくらい、いや大人になってからは出来ないという意味では勉強以上に大事なことだ。
息子は、石垣島でもやや辺鄙なところにある全校児童十数名の小学校に通っていた。クラスは複式学級で、いわゆる学習面では若干の不安はあったものの、それを上回る魅力があったので移住を決めた。魅力とは三つ。圧倒的な自然と、みんなで子育てをする地域社会と、子どもだけで野放図に遊べる環境だ。都会での子育てで、懸命に努力して補ってきた三つだが(そしてなかなか足りていないという実感があった)石垣島では、やすやすと手に入る。お勉強のほうは、自分が補ってやればいい。そっちは、むしろ得だという自負もあった。
学習面では・・・などと失礼なことを言ってしまったが、島の子どもたちの知恵には目を見張るものがあった。道を歩いていると、食べられる草、食べられない草、ヤギが大好きな草などを教えてくれる。近所にスーパーがなかったので、私自身、長命草(という食べられる草)にはずいぶん助けられた。魚は見事にさばくし、釣りに行くときには「弓張り月」なんて言葉を使って潮の満ち引きを考えている。大きな魚を捕まえた少女は、暴れる大物の背骨を足で踏んで折っていた。鮮度を保ったまま大人しくさせるのだ児童の数が少ないので、必然的に年齢の違う子どもが一緒に遊ぶことになる。たとえば鬼ごっこの時には「一年生には二回続けてタッチしない」など、独自のルールを話し合って決めていた。ヤドカリに息を吹きかけて次々貝殻から追い出す遊びに息子が熱中していると「ほんとうに欲しい貝のだけにしといてやれ」と、にいにいが諭す。親に命の大切さを説かれるより、ずっと効くようだった。
イワサキクサゼミというハエくらいのサイズの蝉を生きたままプローチのように胸に付ける遊びがある。地面にたたきつけて蝉を気絶させるのだが、力が強すぎると死んでしまうし、弱いと逃げられる。どこまでが効果的で、どこからがやりすぎかは、何度も試して覚えるしかない。何ごとにもそういう力加減は必要で、たとえば言葉を扱うときにも、大事なことだろう。
(俵万智著「生きる言葉」新潮新書)
最高の遊び場・自然
子どもがゲームよりも面白い、楽しいと言えるものがあるのですね。自然はそういうものだと思います。
そう考えると、私の子ども時代は今の子ども達に比べるとぜいたくだったんだなあと思います。夏休みはほとんど毎日、野山、川、プールで遊んでいました。昆虫採集もしましたし、渓谷で魚やサワガニをとったりして、庭でとれた胡瓜やトマトに塩をまぶして丸かじりしたり、思い出すだけで楽しくなります。
癒し効果抜群
自然豊かなところに行くだけで心身が癒される経験は多くの方がお持ちだと思います。昨年、頭の手術をして18日間入院しましたが、段々息苦しくなってきました。屋上庭園があるので、許可をいただいてそこに出てみました。幾つもの木々が植えられていて花も咲いていました。わずかな自然空間でしたが、すごく心が和みました。蝶や蜂を見るだけでも嬉しくなり、空を見ると鳥が飛んでいました。都会の空気ではありましたが、思わず深呼吸し、神様に「ありがとうございます」と言っていました。
聖書のこんな言葉を思い出しました。
鳥のことを考えてみなさい。蒔きもせず、刈り入れもせず、納屋も倉もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなたがたは、鳥よりも、はるかにすぐれたものです。
新改訳聖書 ルカ 12:24
自然には私達の心身を癒す力があるようですが、その自然を私達のために造ってくださったのが神様です。このお方に感謝して日々生活するとますます元気になります。
子ども達が自然に触れ、偉大な神様の愛に育まれて成長してくれることを祈っています。