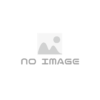サンタクロースの部屋
心の発達は?
子ども達の心の発達はどのようになっているのか? これはなかなかわからないものです。心の発達と言っても心がどこにあるのかが問題になります。おおよそ「脳」と考えられていますが、脳は肉体の一部ですから、脳の発達は体の発達と関係しており、心が脳にあるなら、心の発達も体の発達と関係していることになります。
子ども達にも心の問題が増えている現代、どのようにすることでそういう問題は減らせるのか? とても気になっています。
サンタクロースの部屋
そんな中、朝日新聞のコラムに次のようなのがありました。
折々のことば:2949 2023年12月25日
鷲田清一
心の中に、ひとたびサンタクロースを住まわせた子は、心の中に、サンタクロースを収容する空間をつくりあげている。
(松岡享子)
◇
子どもにサンタクロースの話をするのは、「見えないものを信じる」能力(キャパシティ)を養うためだと、児童文学者は言う。サンタの話を聞いた子の中には、サンタがいなくなってもサンタのいた空間は残る。「ふしぎの住める」この空間は、「のちに、いちばん崇高なものを宿すかもしれぬ」そんな心の場所なのだと。『サンタクロースの部屋』から。
この文章を読んで、気になったのでネットで調べてみました。すると、今度はこういう文章を見つけました。
もう数年前のことになるが、アメリカのある児童文学評論誌に、次のような一文が掲載されていた。「子どもたちは、遅かれ早かれ、サンタクロースが本当はだれかを知る。知ってしまえば、そのこと事態は他愛のないこととして片付けられてしまうだろう。しかし、幼い日に、心からサンタクロースの存在を信じることは、その人の中に、信じるという能力を養う。わたしたちは、サンタクロースその人の重要さのためだけでなく、サンタクロースが、子どもの心に働き掛けて生み出すこの能力のゆえに、サンタクロースをもっと大事にしなければいけない。」というのが、その大要であった。この能力には、確かにキャパシティ―という言葉が使われていた。キャパシティーは、劇場の座席数を示すときなどに使われる言葉で、収容能力を意味する。
心の中に、ひとたびサンタクロースを住まわせた子は、心の中に、サンタクロースを収容する空間を作り上げている。サンタクロースその人は、いつかその子の心の外へ出て行ってしまうだろう。だが、サンタクロースが占めていた心の空間は、その子の中に残る。
この空間がある限り、人は成長に従って、サンタクロースに代わる新しい住人を、ここに迎え入れることができる。
若草幼稚園 2001/12/1 より
親を信じる心
私は牧師ですから、子どもが神を信じるのと、大人が神を信じることの違いに関心があります。
子どもは、まず赤ちゃんの時に親を信じきっています。お母さんのおなかの中で成長してきたことは赤ちゃんの心の成長に大きな影響を与えているはずです。とても安心できるお腹の中で何不自由なく成長しているのです。
その後、お腹から出てくると、泣いてお腹が空いたこと、おしめが濡れて気持ちが悪いとか、眠いことを伝え、お母さんに支えられ、守られていることを体験してさらに親を信じる力が整うのだと思います。しかし、同時に泣かなければ伝わらないこととか、泣いても伝わらないこともわかってきます。それによって自分の意思も育つように思います。
この信じる心がある時期になって「神を信じる力」に繋がっていくのだと思うのですが、今回この「サンタクロースの部屋」という話を読み、子どもの心に「サンタクロースの部屋」なるものがあることでその部屋にイエスを迎えることができるのだと思えました。
9歳の壁
こうした子どもの心の発達はどのあたりで変化していくのかは昔から考えられていました。そういう中、比較的最近、9歳あたりで大きな変化があることが言われるようになりました。ろう学校の先生が聴覚障害のある子が9歳あたりで健聴児と勉強に差が出ることに気が付いたことで見つけられたと言います。いわゆる「9歳の壁」です。
長年「9歳の壁(あるいは10歳の壁)」について子育ての会や講演会で語ってきましたが、子育て通信の222号で「魔の2歳児」、「悪魔の3歳児」、「4歳の壁」、「5歳の中間反抗期」、「小1の壁」などという言葉があることを伝えました。
5歳の壁
最近見つけた本に「5歳の壁」(和田秀樹著・小学館)というのがありました。こういう「壁」という言葉は気になるので、読んでみたところ、
「長年子どもの学力向上に取り組み、受験指導を続けてきた私が多くのかたにお伝えしたいのは、子どもの学力はもともとの素質や遺伝よりも、勉強の方法や取り組み方に左右されやすいということです。そして何より大事なのは、自分から学ぶ意欲を持つ子どもが、最終的にいい結果を出しているという事実です。
そして、子どもがこうした意欲を身に着けるためには、小学校入学までの大人の接し方がとても重要です。5歳前後までに親や周りの大人がどう関わるかによって、その子の人生は大きく変わっていきます。」(p3-4)
と、ありました。
そして、子どもの語彙力が大事だとありました。語彙数を増やすことです。私は子どもの「なぜ?」に煙たがらずに答えてあげること、大人もわからないような質問には一緒に考えたり、調べることが大事だと思っています。
言葉はとても重要です。言葉がその人の人格を作っていきますから、ただ知識としての言葉を増やすだけではなく、良い言葉を蓄え、良い考えを持てるようにしたいものです。
そして、記憶優位なのが9歳までで、そこからは脳の仕組みが変化して、論理的な思考に切り替わっていきます。
ことば
聖書にこんな言葉があります。
初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。
ヨハネの福音書1:1
ここでの「ことば」は「イエス・キリスト」のことです。ですから「イエス・キリストは神であった」となるのです。
そしてこの「ことば」の原語は「ロゴス」というギリシャ語で、「ことば」の他、「理性」とも訳せます。単に口から出てくる音声の「ことば」だけではなく、人の口から出てくる「ことば」は人格の内側から出てくるものなのです。
イエスの「ことば」は神のことばそのものですから、人を愛し、人を生かそうとする素晴らしいことばです。そのようなことばをすべての人が発することができたら何と世の中は良くなることでしょうか。聖書はそういうイエス・キリストの言葉や大事な言葉がたくさんあります。
ユダヤ人は聖書(彼らの聖書は旧約聖書で、私たちクリスチャンはこの旧約聖書と新約聖書の両方で聖書と呼んでいます)を丸暗記するように子どもの時から教え込まれるそうです。それは神のことばを覚えることで良い人格を持つことができるからでしょう。
暗記の良さを取り入れて、幼い内から暗記教育をしているところ、家庭がありますが、悪い言葉をたくさん蓄えたら良くない考えを持つことになります。「聖書教育」はとても大事だと思います。
サンタクロースの部屋にイエス・キリストを迎えて、本当に良いことばを語る人になりたいものです。
マザー・テレサのことばを少し引用します。
世界平和のためにできることですか?
家に帰って家族を愛してあげてください。暗いと不平を言うよりも、あなたが進んで明かりをつけなさい。
説教してきかせても、それは人とふれあう場にはなりません。ほうきをもってだれかの家をきれいにしてあげてごらんなさい、そのほうがもっと雄弁なのですから。
笑ってあげなさい。
笑いたくなくても笑うのよ。
笑顔が人間に必要なの。